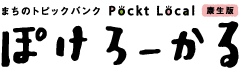59

[ 雑貨・本 ]
2025-03-03
【春のお彼岸】大切な故人にご挨拶に行って、今の気持ちや感謝を伝えませんか?3月17日~23日まで。(岡崎・康生/サラダ館明大寺店/雑学)
今年の「春のお彼岸」は3月17日(月)から3月23日(日)までの7日間。
今年の春分の日(3/21・木祝)を真ん中に挟んで前後3日間が、春のお彼岸とされています。
お彼岸には、仏様の供養をする事で、極楽浄土へ行くことが出来ると考えられており、お墓参りや法要が行われています。
本日は、お彼岸の豆知識やお供えモノに最適な商品をご紹介します。
お彼岸は、日本古来の「先祖崇拝信仰」が「仏教」の教えと融合したもの?

日本文化に定着した「お彼岸」という行事。
春は3月、秋は9月にお墓参りをするという事は知っていても、なぜ 「お彼岸」というのかはご存じない方もいるかもしれません。
「お彼岸」の元になったのは、サンスクリット語の「パーラミター」といわれています。
「完成する、成就する」という意味で、欲や煩悩、苦しみに満ちた輪廻の世界から解脱し、迷いのない悟りの境地に達することを表してします。
この悟りの境地を、この世とあの世を隔てる”三途の川”の向こう岸、すなわちあの世である「彼岸(ひがん)」に例えたのが日本人でした。

日本に昔からある価値観や先祖崇拝の影響で、亡くなった家族やご先祖は「彼岸」へと渡り、迷いや煩悩の無い世界へいくと考えられていました。
そこで、先祖供養をすることでご先祖さまの冥福を祈るとともに、自分自身もいつか迷いのない彼岸に到達できるよう願をかける「お彼岸」という伝統行事が定着していったと言われています。
「春分の日」と「秋分の日」には、太陽の通り道がちょうど真東から真西になるために、彼岸とこちら側の世界(此岸)が通じやすくなると考えられていました。
それで春と秋に「お彼岸」が行われ、亡くなった者と生きる者たちの交流の場が設けられるようになったのです。
春のお彼岸は「ぼたもち」、秋のお彼岸は「おはぎ」

お彼岸と言えばこれ。ぼたもちですよね!
小豆には魔除けの効果があると考えられていて、お彼岸に備えたり食べたりする伝統があります。
ちなみに、季節ごとで呼び方が変わるのはご存じでしたか?
春のお彼岸(3月)は、「ぼたもち」で、春に咲く牡丹(ぼたん)の花が由来となっています。
秋のお彼岸(9月)は「おはぎ」。秋に咲く萩(はぎ)の花が由来です。
両方、季節のお花が由来になっているのも、風情があって素敵ですね。
お線香は、「死者との対話の力」を高める効果がある?!


故人の好きだった物を思い出してみて下さい。
お菓子や、果物、お酒、などを墓前やご仏前にお供えし、故人へ思いを馳せることが供養となります。
食べ物は「日持ちするもの」、「小分で分けやすいもの」が人気で、そのまま飾ることができるお花や、高価なお線香、ろうそくのセットなんかもおすすめです。
故人をしのぶ時にお線香をたく理由を知っていますか?
・故人への食べ物として線香の煙をささげる意味
・汚れをはらい、体や心を清浄にする意味
などは有名ですが、死者との対話力をアップさせるなんて意味もあるようです。
お線香の煙を焚くと、立ち上る煙によって”あの世”と”この世”がつながるとされてきました。
お参りする人の気持ちを煙に乗せて故人へ届けてくれるので、「故人と対話する力」が高まるともいわれており、ゆっくりと会話を楽しめるとのこと。
せっかく訪れたのだから、ゆっくりとおしゃべりを楽しんで近況を報告してきたいですね。
年間行事のグッズ、贈呈品、お返しなど、なんでもご相談に乗ります

ちょっと形式ばった行事や、目上の方に失礼に当たらない贈り物ってどういうモノ?
そんな疑問にも、気軽に相談に乗ります。
現代ではだんだんと伝統文化に対する知識も失われつつありますが、「ちゃんとしたい」「教養のある人としての贈り物をしたい」という場面が出てくることもあると思います。
そんな時に、気軽にお店に足を運んでもらえたら、痒い所に手が届くようなアドバイスや商品選びのお手伝いをさせていただきます。
59