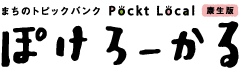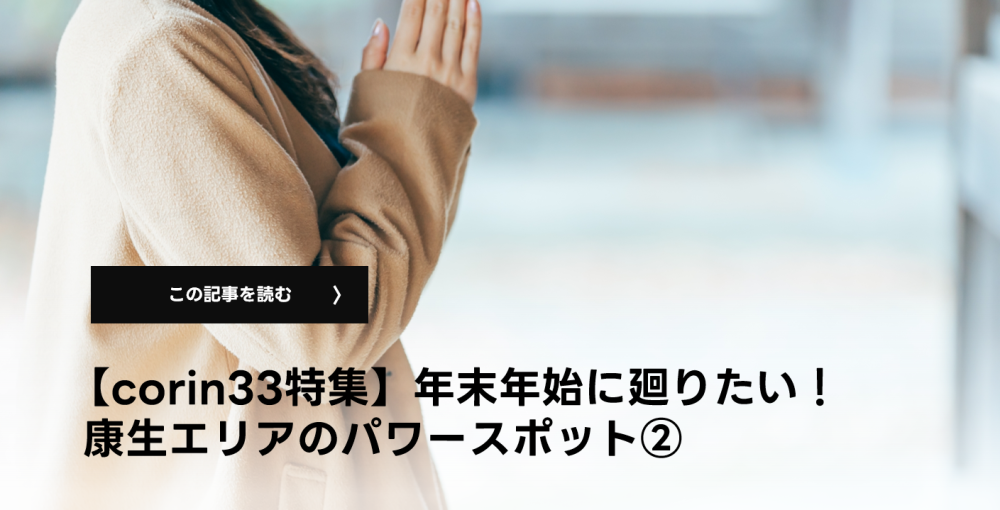45

[ 企画 ]
2024-12-21
【corin30特集】岡崎市・開市500年記念特集① 年表で500年の歴史を紐解く
岡崎市の開市から500年。
康生を中心としたこのエリアは、約500年の長きに渡り、「商いのまち」が続いています。
では500年前から、いったい何が起こっていったのでしょうか?
どんな出来事があったのかを、この記事でご紹介します。
読みながら色々な時代へ思いをはせてみてください。
◆家康公の祖父・松平清康の時代(1524~1531年)

1524 ◆ 大永四年 市場が開かれる(開市)
現在の連尺通りに商人が集まり、市場を開いた。このころから、商業地としての歴史が始まる。
1531 ◆ 享禄四年 現在地に城が移る
松平清康(家康公の祖父)が明大寺から現在の位置に居城を移した事で、お城周辺の菅生川北部(現在の康生エリア)が発展し始める。
⇒『家康公の祖父・松平清康』について、もっと詳しく知りたい!
◆徳川家康公の時代、宿場町として栄えた岡崎(1542~1590年)

1542 ◆ 天文十一年 徳川家康公が誕生
松平竹千代、後の徳川家康公が岡崎城で生誕。龍が昇ったという伝説もある。
1590 ◆ 天正十八年 田中吉政が岡崎城主に
この年、徳川家は関東に入封。替わって田中吉政が岡崎城主となり、「二十七曲り」など、十年をかけて岡崎城下を整備した。
慶長六年には 東海道に宿駅伝馬制度が整備され、岡崎は宿場町として栄えていった。
◆「康生」という名前の成り立ち、明治・大正時代への移り変わり(1872~1912年)

1872 ◆ 明治五年 康生と名付け
旧岡崎城主郭部が「康生」と名付けられる。(明治八年とも) 康生は、家「康」公が「生」まれた地を意味しており、この地に生きる人々の誇りとなっている。
1873 ◆ 明治六年 岡崎城が廃城される
この年発令された廃城令により、岡崎城は廃城となり、天守以下の建物は撤去された。
しかし旧藩士から保存を希望する声が明治政府に多く寄せられ、明治八年に本丸跡は公園として残されることに。
1912 ◆ 大正元年 岡崎電気鉄道が運転開始
明治三十一年には岡崎馬車鉄道の運転が始まり、九年後には康生町まで鉄道が伸びている。
馬車から鉄道に変わったのが大正元年。名鉄岡崎市内線(市電)の始まりだった。この市電の開通が、商業の中心地が国鉄の岡崎駅前から再び康生エリアへと戻るきっかけに。
◆戦前・戦中の岡崎市、夏祭り後の夜に起きた空襲(1926~1945年)

1926 ◆ 昭和元年 開市400周年記念
岡崎市民が開市400周年を祝って、山中城に記念碑を立てる。
1945 ◆ 昭和二十年 岡崎空襲(第二次世界大戦)
七月一九日、夏祭りで大いに盛り上がった日の夜、まちは空襲で壊滅的被害を受けた。
当時の市長が、がれきの山と化した光景を前に呆然と立ち尽くす写真が残っている。
◆戦後、復興の道のり(1949~1952年)

1949 ◆ 昭和二四年 復興モデル都市に指定
戦後一週間で路面電車が復旧し、青空市などのバラックが立ち並んだ。
次の年には区画整理事業も進み、戦災都市の中で最も速やかな復興を成し遂げたとして、全国の「戦災復興モデル都市」の指定を受けた。
1952 ◆ 昭和二七年 東海道が国道一号線に
江戸時代の五街道に数えられた東海道は長らく旅人たちの主要道路であったが、国道を整備する際に国道一号線に指定された。
◆商業施設「新天地」、「二七市」の誕生(1952~1955年)

1952 ◆ 昭和二七年 新天地がオープン
敗戦間もない頃、店を焼失した人や露天商の人々が集まって出来た岡崎マーケットが、商業施設「新天地」と名前を変え、岡崎シビコ3号館(現在の岡崎日本語学校)の場所にオープンした。
1955 ◆ 昭和三十年 闇市から二七市が始まる
終戦後、中央マーケットという闇市がきっかけで、この年の十二月十二日に最初の二七市が開催。
昭和三七年頃には出店が200軒を超えた。
現在も八幡町発展会が中心となって、2と7が付く日に八幡通りで定期開催されている。
◆続々とオープンする大型商業施設、繁華街にまで発展した岡崎市(1971~1992年)

1971 ▼ 1976年 大型商業施設が進出
松坂屋開業(昭和四六年)、セルビ開業(昭和四七年)、メルサ開業(昭和四八年)、シビコ開業(昭和五一年)と、大型商業施設が中心市街地に次々とオープンした。
1992 ◆ 平成四年 三河一の繁華街に発展
大型施設の誘致により康生エリアは三河一の繁華街へと成長。
「康生」に遊びに行くことはステータスとされ、芸能人を呼ぶなどのイベントも開催された。
車で街をぐるぐる徘徊しながらナンパを行うグルグル族なども現れた。
◆QURUWAエリアの再開発、現在に至るまで(2010年~現在)

2010 ◆ 平成二二年頃 中心市街地の衰退
車社会が進み、郊外の大型ショッピングモールが出現すると、いわゆるドーナツ化現象で人が外へと流れ、街に来る買い物客も大幅に減少。
一時期、一世を風靡した大型施設も次々に撤退していった。
2015 ◆ 平成二七年頃 QURUWAエリア再開発
駅や公園など街に存在する拠点をQの形に結んだ「QURUWAエリア」の再開発が5年かけて進み、暮らし方や過ごし方の多様性を生み出す実験が行われた。現在は、康生エリアへの出店も増え、賑わいが戻りつつある。
45


[ 企画 ]
【corin30特集】岡崎市・開市500年記念特集① 年表で500年の歴史を紐解く